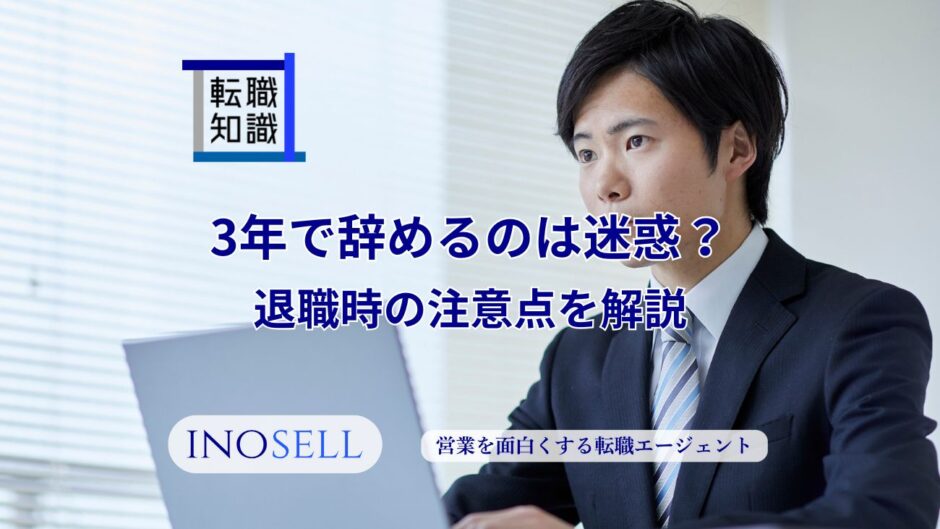「3年で会社を辞めるのは迷惑かもしれない…」と不安に感じる方も多いでしょう。ですが、近年ではライフスタイルやキャリア観の多様化により、3年を一区切りに転職を考える人も増えています。つまり、3年で辞めること自体は特別なことではありません。
大切なのは「辞め方」と「その後の行動」です。前向きな理由で丁寧に退職すれば、会社に迷惑をかけずに次のステップへ進むことが可能です。この記事では、3年で辞めるのが一般的と言われる背景や、円満退職のコツ、転職を成功させるためのポイントを解説します。
目次
3年で辞めることは会社に迷惑?
3年で会社を辞めることについて、「迷惑になるのでは」と悩む方も多いかと思います。結論から言えば、状況や退職理由によります。ここでは、3年で辞めることが一般的である理由や、注意すべき点を詳しく解説していきます。
3年で転職する人の割合
厚生労働省の「新規学卒就職者の離職状況」(令和5年3月卒業者の追跡調査)によると、新卒で入社した人のうち3年以内に離職する割合は、大卒で31.5%、高卒で36.9%となっています。
つまり、およそ3人に1人が3年以内に職場を離れていることになります。この数値は過去20年以上ほぼ横ばいで推移しており、「3年で辞める=珍しいこと」ではありません。
また、他の民間調査でも「初めての転職時期」として最も多いのは入社3年目前後で、全体の約25%を占めるとされています。多くの人が3年という節目で環境を見直し、キャリアの方向性を再考しているのです。
参考データ:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和5年3月卒業者版)」
3年で転職を繰り返すと印象は良くない
一方で、「3年で辞めること」自体は珍しくないものの、短期間での転職を何度も繰り返す場合には注意が必要です。
採用担当者は、以下のような懸念を抱くことがあります。
- 責任感や粘り強さが不足しているのでは
- 職場に適応する柔軟性がないのでは
- キャリア形成が中長期的に見えていないのでは
特に同じ業界や職種での転職を考える場合、「長期的に働ける人材かどうか」は評価の重要なポイントになります。3年での退職が一度であれば問題視されにくいですが、それが繰り返されると信頼を得づらくなる可能性があります。
「3年は辞めるな」と言われる理由
「3年は辞めるな」というアドバイスを耳にすることは少なくありません。この理由には、職場での信用やスキル形成といった重要な要素が含まれています。ここでは、なぜ3年働くことが推奨されるのか、その理由について解説します。
すぐに辞める人ではないという信用が得られるから
3年以上働くことで、職場や会社から「責任感がある人」として信用を得やすくなります。採用側にとって、短期離職が頻繁な経歴は「仕事に安定的に取り組むことが難しい」といった印象を与えることがあります。
そのため、最低でも3年働くことで、採用時や転職時にプラスの印象を与え、信頼される人物であることを示す根拠になります。また、同僚や上司にとっても「途中で投げ出さない人」という安心感が生まれ、職場での評価が高まりやすいです。このような結果につながるため、多くの人が3年を一つの区切りとして捉えるのです。
ある程度のスキルや経験が得られるから
3年という期間は、仕事を通じて基本的なスキルや業界の知識を得るのに適した時間です。特に新しい環境や職種に就いた場合、最初の1年は学びの時期、2年目は身につけたスキルの発揮、そして3年目には自立的に業務を進められる段階に到達しやすいです。
このように、数年単位で働くことで、適応力や専門知識、さらには問題解決能力といった重要なビジネススキルが養われると言われています。また、転職市場においても「3年以上の経験を持つ人材」は即戦力として評価されやすい傾向にあります。こうしたメリットを得るためにも、3年働くことが推奨されるのです。
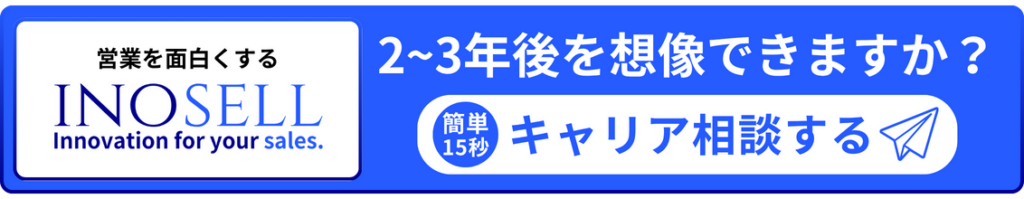
3年働けば辞めてもいいという考え方の理由
「3年働けば辞めてもいい」と考える理由には、スキルアップやキャリア形成の観点が挙げられます。ここでは、その背景としてどのような理由があるのかを詳しく解説します。以下では、複数社を経験することのメリットや、一時的な感情ではない転職の意義、さらには年収アップの可能性について触れていきます。
複数社を経験した方がスキルアップしやすいから
3年で会社を辞めることを考える背景には、複数社を経験することでスキルアップにつながるという考えが挙げられます。3年間働いた後に転職を考える人は、異なる職場環境や業務プロセスを学びたいという意識が強い傾向にあります。
一つの職場で得られる経験やスキルには限りがありますが、他の会社で働くことで新しい知識や視点を取り入れられます。特に専門性が求められる仕事の場合、自身の価値を高めるために幅広い経験を積むことは非常に重要です。
転職市場でも、複数の企業を経験している人材は柔軟性や適応力が高いと評価されやすいです。そのため、3年という区切りで転職を選ぶのは、スキルアップを目的とした前向きな選択といえるでしょう。
一時的な気持ちではない可能性が高いから
3年という時間を費やした上で転職を検討する人にとって、決断は軽率なものではないと考えられます。短期間で辞めると「一時の感情」による行動と捉えられることが多いですが、3年間には一定の経験や成長が含まれるため、慎重に考えた上での選択であると見られます。
例えば、職場の環境や仕事内容が合わないと感じた場合でも、すぐ辞めるのではなく、一定期間は改善の努力をした可能性が高いでしょう。
また、3年働いたことで自分のキャリアの方向性を明確にし、「今後どのような職種や会社が自分に合うのか」を判断できる準備期間にもなります。
こうした熟慮の結果であることから、3年で辞めることは単なる迷惑行為ではなく、計画的なキャリア選択として評価されることが多いです。
年収をアップさせやすいから
3年ほど働いた後に転職を選ぶ理由のひとつに、年収アップが挙げられます。多くの場合、1社に長く留まるよりも、一定のスキルや経験を携えて転職活動を行う方が、給与条件を向上させる交渉がしやすいとされています。
特に今回の転職が初めてのケースであれば、「3年間で積み重ねた経験」をアピールポイントとして市場価値を高めることができます。また、他業界への転職や専門知識を活かしたキャリアチェンジの場合、企業側も優秀な人材を確保するために、前職以上の給与や待遇を提示する傾向があります。
もちろん転職による年収アップには準備が欠かせませんが、適切な計画を立てれば、3年で辞めることがキャリア形成の重要なステップとなるでしょう。
3年で辞めても迷惑にならないための退職方法
3年で辞める場合、多くの人が職場に迷惑をかけてしまうのではと不安に思います。しかし、適切な退職方法を取れば、会社に与える影響を最小限に抑えることが可能です。ここでは、退職の際に注意すべきポイントを詳しく解説します。
退職理由はポジティブなものにする
3年で辞める際には、退職理由をポジティブなものにすることが重要です。例えば、「自身のスキルをさらに深めて成長したい」「新しい分野に挑戦したい」といった前向きな理由を伝えると、会社側も理解しやすくなります。
逆に、「職場環境が悪いから」「上司が気に入らないから」といったネガティブな理由を述べると、会社との関係性が悪化する恐れがあります。ポジティブな理由を明確にすることで、円満に退職でき、転職先でも良好な印象を保つことができます。
現職の悪口を言わない
退職の際には、現職や職場の悪口を避けることが重要です。どの仕事や会社にも良い点とそうでない点があるものですが、悪口を言ってしまうと、退職後のあなたの評価に影響を与えかねません。
また、悪口は周囲の同僚や上司に伝わる可能性が高く、迷惑をかける要因になることがあります。たとえ不満があっても公式な場では口にせず、建設的な姿勢を保つことが大切です。特に転職先で「前職の悪口」を語ると信頼を失うリスクがあるため注意しましょう。
引き継ぎは余裕を持って行う
退職時の引き継ぎは、会社や同僚に迷惑をかけないための基本的なマナーです。特に3年で辞める場合、周囲に「突然辞める」という印象を与えるとトラブルになりかねません。
最低でも1ヶ月以上前に退職の意向を伝え、後任者や他のメンバーに自分の業務を詳細に引き継ぐ時間を確保しましょう。また、引き継ぎの際には、業務マニュアルを作成して次の担当者がスムーズに業務を行えるよう配慮することも効果的です。余裕を持った対応により、感謝されつつ職場を離れることができるでしょう。
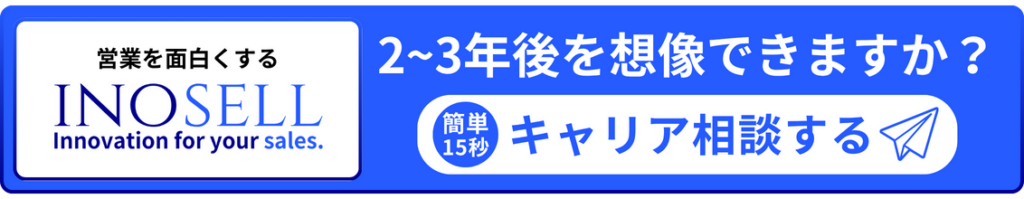
3年で辞めて転職する際の注意点
3年で辞めて転職すること自体は一般的であり、迷惑とされるわけではありません。しかし、転職を成功に導くためにはいくつかの注意点があります。ここでは、3年で辞める際に気をつけるべきポイントについて解説します。
とりあえず転職という気持ちで動かない
「今の仕事は嫌だから」と具体性がなく曖昧な理由で転職を決めると、現職に迷惑をかけるだけでなく、次の職場でも同じ悩みを抱えてしまう可能性があります。
環境だけを変える転職がうまくいきにくいとされる理由は、根本的な問題解決になりづらいためです。転職動機を整理し、自分が本当にどのような仕事や職場環境を望んでいるのかを明確にすることが重要です。
必ずしも年収がアップするわけではない
転職すれば必ず年収が上がるとは限りません。3年で辞める場合、まだ専門的なスキルや経験が不足している場合も多く、転職先での条件が現職より劣るケースがあります。
年収アップを目指す場合は、具体的なスキルを習得するか、経験を積んで価値を高める必要があります。転職活動をする前に、自分の市場価値や求める条件をよく調べ、適切な目標を持つことが肝心です。
未経験な業界や職種への転職は簡単ではない
未経験の業界や職種への転職を考える場合、相応の努力と準備が必要です。3年の経験があるとはいえ、業界や職種が変わるとゼロからスタートする必要が出てきます。
事前に転職先の業界や職種について調査し、自分のスキルがどれだけ適応できるかを確認することが重要です。また、企業側としても、未経験者を採用するリスクを懸念するため、意欲や将来性をアピールする工夫が求められます。未経験転職の壁を最小限にするには、入念な準備が必要不可欠です。
3年で辞めることは迷惑かに関するよくある質問
3年で仕事を辞めることが職場や会社に与える影響について、多くの人が疑問を抱きます。ここでは、よくある質問を取り上げ、わかりやすく解説していきます。
会社を3年で辞める理由は何ですか?
3年で会社を辞める理由には、仕事が合わないと感じることや、職場環境が悪いと感じることが多いです。また、成長機会が少ない、教育体制が整っていない、といった場合も挙げられます。
他にも、転職によるスキルアップを目指す人や、家族やプライベートな事情で退職を決断するケースもあります。このように、理由は人それぞれであるため、まずは自分の状況を冷静に把握することが大切です。
3年で離職する人はどれくらいいますか?
前述の厚生労働省のデータによると、新卒社員の約30%が入社後3年以内に離職しています。この傾向は過去20年間ほぼ変わっておらず、多くの人が3年で職場を辞める選択をしていることがわかります。
また、20代全体では転職経験率が高く、特に短期離職は若い世代にとって珍しいことではありません。このようなデータから、3年で辞めることが特別なケースではないことが理解できるでしょう。
社会人3年目で辞める人は多いですか?
社会人3年目で辞める人は多いとされています。調査によると、初めての転職をする時期として最も多いのが「3年目」です。入社後3年間働くことで、職場や仕事の適性について判断しやすくなるため、このタイミングで退職を決断する人が増えるようです。
また、3年目は仕事にも慣れてきた一方で、将来のキャリアを真剣に考えやすい時期とも言えます。このため、3年目での転職は一定の合理性があると考えられます。
仕事を辞めるなら何年目がいいですか?
仕事を辞めるタイミングは個人の状況によりますが、一般的には2〜3年の経験を積んだ後が良いとされています。短すぎる期間で辞めてしまうと、「忍耐力がない」と見なされる可能性がありますが、3年程度の勤務を経ていれば、一定のスキルや経験をアピールしやすくなります。
ただし、職場環境が極端に悪い場合や健康を害するほどのストレスを感じる場合は、年数に関わらず早めの判断も必要です。
3年で退職したらいくらもらえる?
3年で退職した場合の退職金は、企業規模や制度によって異なります。中小企業では支給されない場合もありますが、大手企業や退職金制度が整っている会社では少額でももらえることがあります。
日本の平均的な退職金支給額は、勤続10年未満で数十万円程度とされています。ただし、退職金だけでなく、未払いの有給休暇や残業代があれば、それも合わせて請求できるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
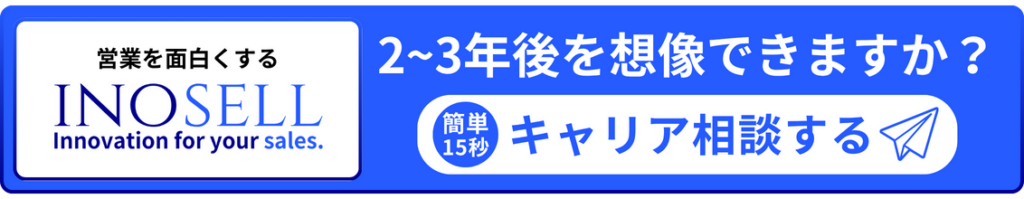
まとめ
3年で辞めることが迷惑かどうかは、辞め方や職場環境、転職理由によって異なります。3年という期間は、次のキャリアを考える上で区切りとなることが多い一方、短期離職に対する印象が良くない場合もあります。
そのため、退職時には引き継ぎを適切に行い、ポジティブな理由を伝えることが重要です。転職を成功させるためには、自身のスキルやキャリアプランをしっかりと見直し、次の職場での成長を視野に入れる必要があります。
「3年で辞める」ことは個人にとって一つの選択であり、前向きに行動することでその後のキャリア成功につなげられるでしょう。あなたの決断が充実した仕事人生の一歩となるよう、計画的に進めてください。